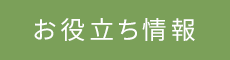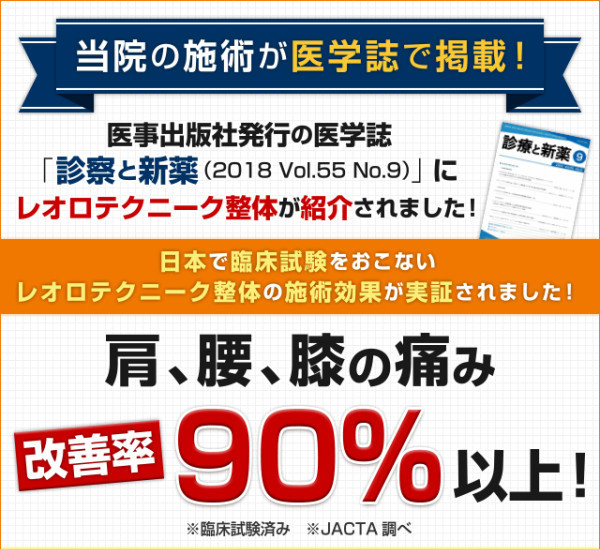院長 髙木稔之 ごあいさつ
「脊柱管狭窄症って病院で言われて、もう手術しかないってことなんですけど、やっぱり手術は怖いんでどうにかならんかと・・」
どうにか歩き、椅子に座ったその患者さんは、辛そうに顔をゆがめて腰をさすっていた。
患者さんの様子を見て髙木は、安心のような、ホッとする感情を覚える。
その感情は、手術と言われても「手術しないでどうにか良くならないか」と粘り強く思い直すことができた患者さんへの共感かもしれない。
そして、改めて気を引き締めて、こう伝える。
「大丈夫ですよ。必ず改善させますから。ご安心ください」
体の仕組みの奥深さに触れた日
「柔整師はええで。髙木くんもなった方がええ。学校に推薦してあげるから、そこに行きなさい」
「柔道整復師は食いっぱぐれない」と言われた時代、こんなふうに誘われて、高校卒業後の進路を決めた治療家は少なくない。髙木もその一人だった。
漠然と、「パソコンに興味あるし、パソコン関係の専門学校にでも行こうかなぁ」と考えていた進路。それを、母親とその友人の柔整師の勧めで、ゆるりと方向転換させた。高校三年生の秋だった。
「まぁ、資格取るだけ取っとくか。そのあと別のことをしてもええし」
そんな気持ちで柔道整復師の専門学校を受験し、運よく合格。
それが髙木の治療家人生の始まりだった。
髙木:「治療家になったる!みたいな気合いはほとんどありませんでしたね。当時は柔整師がすごく儲かっていた時代だったので、それに乗るか、みたいな感じで。まさか現在のような治療方針になるだなんて、全く夢にも思っていなかったんです。」
そのように大した興味も持たずスタートさせた治療の勉強も、いざ始まってみるとがらりと印象が変わった。
目の前で、人の体が大きく変化する。
髙木を最も驚かせたのは、ぎっくり腰で歩くことさえできなかった人が、治療を受けた直後にすたすたと歩き始めたことだった。
「さっきまで歩けへんかったのに!すごい・・」
初めは、まるで魔法を見ているような驚きばかりを感じていた。そのうち座学と実技を進めていくにつれ、人の体の部位は内部で複雑に連携しており、そのかかわりを正常に戻すことで痛みや不調が治ることが理論的に理解できるようになっていくと、好奇心の強い若者だった髙木は、勉強にのめりこむようになる。
「人の体って、奥深くて面白い」
髙木:「僕の治療家人生はそこから始まったんじゃないかと思うんです。普通は、柔整の専門学校に進むと決めたときがスタートなんでしょうけど、僕の場合は、高い志があったわけではないので。
でもその「低い志」しかなかった僕を夢中にさせてくれた。人の体って本当に面白いです。つながっている不思議は、いくら学んでも飽きないですね。当時から今までずっと勉強しています。」
「資格を取ったらやめてもいいや」の心境は一転する。理論を学ぶ座学と、実際に体に触れて学ぶ実技。そして、亡くなった方の体をお借り(献体)して学ぶ実習もあった。それらを通して髙木は自然と「治療家になる」と心に誓うようになった。
「卒業したらすぐに院で働いて、いずれは独立しよう」
しかし、描き始めた青写真も、あるきっかけでその形を変えることになる。
引かない腰の痛みにいら立つ日々
 「腰が痛いんで、ちょっとシフト減らしてもらってもいいですか・・」
「腰が痛いんで、ちょっとシフト減らしてもらってもいいですか・・」
1人暮らしをしながらの専門学生生活。親に負担をかけるわけにはいかないので、勉強の傍ら、居酒屋でアルバイトをして収入を得ていた。
昼は学校で学び、そのあと深夜まで居酒屋で働く。この忙しい生活が、髙木の体に異変をもたらした。どこかにぶつけたわけでも、ひねったわけでもないのに、腰が痛くて仕方ないのだ。
腰が痛い。腰が痛いせいで、何もできない。
20歳という若さで、体力だけには自信があり、体の不調なんて感じたこともなかった髙木にとって、「腰が痛くて動けない」という状態はひどいストレスだった。勉強をしていても、座り方ひとつに気を遣う。居酒屋で以前のようにきびきびと動き回ることもできない。そして、当然生活に制約はかかるしバイト代も減ってしまう。
「どうにかしてすぐに治さんと」
焦りを感じた髙木は、整形外科や整骨院に通い始める。のんびりしてはいれない。痛みが長引けば長引くほど、不便な生活が続き、自分のストレスもかさんでいくのだ。
しかしそんな髙木の思いとは裏腹に、腰の痛みは一向に良くなる気配を見せてくれない。
「病院にも整骨院にも、こんなにせっせと通っているのに・・」
髙木の脳裏に、「幻滅」という言葉が浮かんだ。
髙木:「柔整師を目指して一生懸命学んでいる最中にですよ、自分の腰を柔整師が治してくれないなんて、本当に幻滅しかありませんよ。病院に行っても良くならないし。あぁ、柔整師ってそんなもんなのかって思うしかありませんでしたね。」
初めて知った、鍼灸のすばらしさ
 志半ばどころか、今まさに歩み始めたばかりのところなのに、躓かされてしまった。「なんの皮肉なのか」と恨みをぶつけたくても、どこにぶつければいいかすらわからない。
志半ばどころか、今まさに歩み始めたばかりのところなのに、躓かされてしまった。「なんの皮肉なのか」と恨みをぶつけたくても、どこにぶつければいいかすらわからない。
そんな髙木の愚痴を、ある友人が聞きつけ、こんなことを言ってくれた。
「鍼灸に行ってみれば?いい先生を紹介するよ」
え・・鍼灸?
柔整の専門学校で学ぶ学生なのだから、治療の方法の一つに鍼灸があることくらいは知っていた。ただ、髙木にとっては鍼灸とは、「気」という言葉を盾に小難しい説明をこねる分野だという印象しかなく、自分にはあまり関係がないと思っていたのだった。
そんな鍼灸を勧められ、当然一瞬戸惑った。しかし、病院と整骨院で良くならないのだから、ダメもとで何かしらやってみるしかない。
「よくわからんけど、行ってみるわ」
鍼灸への期待はあまり持たず、ただただ焦りばかりを胸に、鍼灸院の戸をたたいた。
鍼灸院の先生は、気さくで人が良かった。髙木の腰の様子を検査し、すぐにてきぱきと治療を施すだけでなく、なぜこんなふうに痛くなったのか、なぜその痛みが治まらないのか、簡潔でわかりやすく説明をしてくれた。
その説明が、髙木にとってはとても新鮮だった。
鍼灸と言えば「『気』『血』『水』の循環が・・」やら、「ここから『気』が入って・・」やら、髙木にはなかなか理解できない、しかし一部の鍼灸オタク的な人間にはひどく喜ばれる、独特な説明が繰り広げられるものだとばかり思っていたからだ。先生の説明は、西洋医学の観点も用いながら行われる、誰にでもわかりやすいものだった。
そして、良いのは説明だけでなかった。鍼灸の効果は髙木の腰痛にすぐに届き、初回の治療でだいぶ楽になったのを実感した。
何度か通っているうちに、今まで整骨院や整形外科に通ってヤキモキしていたのがウソかと思えるほど、痛みはスッキリと引いていき、勉強にもバイトにも支障が出ないまでになった。
「これが鍼灸か。自分は今まで誤解をしてたんかもしれない」
鍼灸の効果と、わかりやすさ。それらを身を持って学んだ髙木は、ある決心をする。
「自分も鍼灸を学ぼう」。
髙木:「その鍼灸の先生との出会いは、人生を変えてくれましたね。鍼灸に対する印象や考え方だけでなく、治療の方針や説明の仕方、治療家としてのあり方まで教えてくれたと思っています。
その後、その先生にお会いすることは残念ながらないのですが、あの体験、腰の長引く痛みとそれが治った感動は、忘れることはないですね。」
学校に通いながら現場で実務を積む日々
 柔整師に加えて鍼灸師の資格取得を目指すことにした髙木は、柔整師の学校を卒業した後、鍼灸師の資格を取得するための専門学校に通い始めた。
柔整師に加えて鍼灸師の資格取得を目指すことにした髙木は、柔整師の学校を卒業した後、鍼灸師の資格を取得するための専門学校に通い始めた。
柔整師の資格は無事に取得できたので、もう現場に立って患者さんの体に触れることができる。とにかく実務を積むことが何よりの勉強だと考えていた髙木は、日中は鍼灸の専門学校に通いながら、朝と夕方に整骨院で働き始めた。
非常にハードな毎日だったが、同級生のほとんどは同じような生活をしていたし、何より、自分が学んだことを現場で活かせるようになったのが嬉しかった。
髙木が働き始めた整骨院は、地域で分院展開をし、多くのスタッフを抱える経営スタイルの院だった。
整骨院や整体院は、いまでこそ個人規模の院が多いが、当時はこのように分院もスタッフも多いスタイルの院が主流だった。そのため、髙木の将来的な構想も自然とそこに集約されていた。
自分もいずれは整骨院を開業し、分院を持つなどしてやっていく。
そう思い描きながら整骨院で働くのは、楽しくやりがいのあることだった。
初めて対応した患者さんのことは、今でもよく覚えている。30代後半の主婦で、髙木のマッサージを気に入ってくれ、その後も指名してくれるようになった。
「自分はマッサージが得意なんやな」
そう思うようになってからはさらに、その院で一生懸命働くようになっていた。
髙木:「時代がそうだったから、としか言えませんが、当時は整骨院にマッサージ目的で来る人も少なくなく、それが可能になる保険制度がまかり通っていたんですね。だから私自身も、「患者さんの不調を治す」という気持ちよりは、「マッサージして気持ちよくなってもらって、また来てもらう」という考えで現場に立っていました。」
身構えてしまう自分への嫌悪感
 今ほど、柔整師が扱う保険へのチェックも厳しくなく、患者側からしても「数百円でちょっとコリをほぐしてもらう」という感覚で通うのが普通だった時代。髙木の整骨院に対するイメージや考え方がその通りになるのも、ある点では仕方のないことだった。
今ほど、柔整師が扱う保険へのチェックも厳しくなく、患者側からしても「数百円でちょっとコリをほぐしてもらう」という感覚で通うのが普通だった時代。髙木の整骨院に対するイメージや考え方がその通りになるのも、ある点では仕方のないことだった。
しかし、やはりそれではうまくいかないこともあったのは事実だ。
例えば、稀に来る重症患者への対応。
「ぎっくり腰で動けない」「急に膝が痛くなって歩けない」、こんな症状は、ちょっとマッサージして気分良くなってもらうだけではとても改善させることはできない。そのような重症患者がやってくると、髙木に限らず院内のスタッフ全員が自然と身構えた。身構えるということは、治せる自信がないことの表れでもある。
髙木:「おかしいですよね(笑)。自分自身、あんなに腰が痛くて困っていたのに、痛くて困っている人が来ると身構えるなんて。当時はそういうもんだと思っていたけれど、今は当時の自分に「何やってんねん、ちゃんと治せよ」って言ってやりたいですよ。」
髙木が、重症患者を受け持つことも何度かあった。しかし、当時の技術力では治してあげることはできなかった。
整骨院は重症患者向けのところではないから、治せなくて当たり前。
そんなあきらめを持ちながらも、やはりどうしても疑念がわいてくるようになる。
「自分のあんなにつらかった腰痛を、鍼灸の先生は治してくれたやんか」
髙木が腰痛に苦しんだときに頼った鍼灸師の先生は、「ぎっくり腰は一回の施術で治る」と言っていた。髙木の耳には、それは強がりでも誇張でもなく紛れもない事実として届いていた。
だからこそ、今の自分のスタンスはおかしいと思える。治せる治療家が確かにいるのに、自分は何度通ってもらっても治してあげることができない。
徐々に、強い無力感に襲われるようになっていった。
自分はこのままでは、治療家としてちゃんとした治療ができるようにはなれない。
何かが足りないからだ。
何だろう。何が足りないのか。
―――――やはり、鍼灸をもっと学ばなくてはならないか。
髙木:「結局のところ、鍼灸の先生が自分を治してくれたこと、わかりやすい説明をしてくれたことがずっと心に残っていたんですよね。あの経験がなければ、今でも慰安目的のマッサージだけをやる柔整師のままだったかもしれません。
当時、多くの整骨院のスタンスが慰安マッサージ主流だったにも関わらず、それに流されきってしまうことなく、途中で「ちゃんと治せる治療家にならなきゃ」と方向転換することができたのは、本当に幸いなことだと思いますね。」
「治せる」治療家になるために
 鍼灸の現場をもっと学ばなければならないと考えた髙木は、働いている整骨院の分院の中でも、鍼灸を取り扱っている院に移った。
鍼灸の現場をもっと学ばなければならないと考えた髙木は、働いている整骨院の分院の中でも、鍼灸を取り扱っている院に移った。
その院での鍼灸に対する考え方、説明の在り方や技術そのものは、髙木が最も理想とし、目指している、髙木の腰痛を治してくれた先生のものとはだいぶ異なっていた。正直に言えば、求めていた質ではなかった。それでも現場を学べるのだからと、髙木はそこで見聞きし体験したことを糧にするべく、懸命に働いた。
とにかく、いち早く「治せる治療家」にならなければならない。そのためには鍼灸が最も有効だし、また自分に足りないところでもある。
鍼灸師の学校も最短の3年で卒業した髙木は、卒業後すぐに整形外科の個人クリニックに就職した。
そこは、整形外科での治療と鍼灸の治療を併せて行うクリニックで、体に痛みを訴えて病院に来る、つまりある程度重症な患者さんに対して、鍼灸によるケアを行うことができる。
鍼灸師としての経験を積むことができたのはもちろんのこと、クリニックで働いた一年間を通じて、髙木が学んだことはもう一つある。それは、「病院の、患者さんへの処方の方針」だ。
柔整師・鍼灸師としてやっていくなら、病院との関係は絶対に切り離せない。痛みがある人の多くは、まず病院へ行く。そしてその中の一部の人が整骨院に来る。その時に、病院がその人に対して何をしたか、どういう見解を示したか、ということは、しっかり理解してあげなくてはならない。
髙木にとって、クリニックで働いた期間で得たことは病院の考え方だった。病院は腰や足が痛い人に対してこんなふうに説明し、治療をする。それは必ず知っておかなければならないことだった。
クリニックで1年働いた後は、整骨院の分院長として院の立ち上げから携わり、経営というものに触れる経験をした。
柔整師、鍼灸師。
そして病院での経験。
整骨院立ち上げのノウハウ。
必要な技術と知識は、すべてそろったかのように思えた。
しかし、どうしても満足しきれない自分がいる。
自分は、重症な患者さんが来ても治せるのか?
それだけの技術と自信があるのか?
自分の腰を治してくれた、あの鍼灸師の先生のように。
いくら時間が過ぎても、知識を増やしても、結局はそこに立ち返ってしまう自分がいる。
そうだ、あの先生が自分の原点なのだ。
原点に却らなくていいのか?このまま進んでいいのか?
そう考え始めると、そのまま自分にゴーサインを出すことは、どうしてもできなかった。
「先生のところに行って弟子入りさせてもらおう」
髙木:「それで数年ぶりに再会して弟子入り・・ ってなれば、感動的だったんですけどね。残念ながらそうはいきませんでした。その先生は治療家はもうやめていて、どこにいらっしゃるかも突き止めることができませんでした。
なので、その先生の流派に弟子入りすることにしたんです。
先生の流派だけあって、僕が求めている考え方がそこにはありましたね。最初は先生に会えなくてちょっとがっかりしましたけど、前向きに考え直して弟子入りしたのは、いい選択だったと今でも思っています。」
治療家としての方向性を確立した1年間
 改めて鍼灸を学ぶことで、髙木の得たものは大きかった。
改めて鍼灸を学ぶことで、髙木の得たものは大きかった。
何より、「治せる治療家になる」ことを第一に置いた指導が、ありがたかった。
鍼を打つことは誰にでもできるのだから、いち早く技術を身につけなさい。
患者さんの体を治すのは、技術ではなく感覚勝負。
だから、とにかく一人でも多くの患者さんの体に触れて感覚を身に付け、独立しなさい。
それまで、心のどこかに常にあった迷いや不安が、すっと消えていくのが感じられる日々だった。すべてが自分の求めているもの、つまり「患者さんを治せるようになりたい」という思いにストレートにつながっていく。
教えられたことを、いつまでも宝の持ち腐れにしておいてはいけない。
1年間の学びの期間ののち、髙木は独立をした。
髙木:「さぁ、ようやくいよいよ独立ですよ。独立の際には弟も一緒だったので心強かったし、テナントもすぐに見つかって、順調な滑り出しでしたね。
今までの経験を活かして、鍼灸の先生のところで学んだ考え方を基に、一人でも多くの患者さんを良くしていくことだけを目指せばいい。そんな風に思っていました。何も障害なんてないだろうし、きっとこのまま上り調子にうまくやっていけるだろう、なんてね。今考えると本当に若いし、世間知らずですよね。」
世間知らずでしたよね、と笑う。
そう、滑り出しは順調でも、その後に大きな試練が待ち受けていた。
突然の通達
テナントはすぐに見つかった。弟も助けてくれる。以前働いていた整骨院で担当していた患者さんも、ちらほらと来てくれる。
店を構えていれば次第に存在は認知されていくだろうし、そのうち地元の人も来るようになって、徐々に売上も安定するだろう、という考えに疑念はなかった。
院のスタンスとしては、整骨院でありながら慰安マッサージも行う、よくあるスタイルのもの。柔整の学校で学んでいる学生にも、助手のアルバイトをさせていた。患者さんの入りが悪いかな、と思えば、業者に依頼してチラシを作り、まいた。
その場しのぎの感はあるものの、「まぁこんなもんだろう」と思いながら、毎日現場に立っていた。
髙木いわく「ゆるゆる」な立ち上げ、そして毎日。
ある日、そのゆるい日々が一気に覆される。
郵便受けに、見慣れない硬質な封筒が入っている。
差出人は「近畿厚生局指導監査課」。
「監査?」
急にひどく胸騒ぎがして、急いで封を切る。中にはこう書いてあった。
「3週間後に指導を行うので指定したカルテを持ってくること。指定カルテは指導前日の午後3時にファックスする。正当な理由なき欠席や、内容が疑わしければ監査に移行することもある。」
監査とは、事実上の免許停止だ。
「うそやろ・・」
指導の対象となった原因には心当たりがあった。現役の学生、つまり柔道整復師の資格をまだ取得していないスタッフに「助手」以上の仕事をさせたことだ。
同じ業界に身を置く先輩たち、そして学校の先生からは、そういう調査が行われているというのは聞いていた。しかし誰もが、「そんなの他人事」という口ぶり。なぜなら、柔整の学校に通いながら整骨院でアルバイトをする学生に、多少現場を任せてしまうというグレーなことは、どこの院でもやっているという認識があったのだ。
しかし現実はそう甘くなかった。
ダメなことはダメ。
そして、髙木の院ではその「ダメなこと」をやっていて、裏も取られている。患者さんへの調査もすでに済んでいるとのことだった。
学校の先輩に聞いてみると、思わぬ返答があった。
「それは免許はく奪になるかもしれないよ」。
髙木:「「血の気が引く」とはまさにこのことかという感じでしたね。正直なところ、「みんなやっていることなのに自分だけどうして」っていう気持ちもあったんです。でもそれどころじゃなく、連日呼び出されて調査されて、もう本当に参りました。
そして、自分が今の柔道整復の制度にそぐわないことをしてしまったという思いが日に日に強くなっていきましたね。」
現状の制度に対する不信が徐々に
調査によって指摘されたのは、学生を現場に立たせたことだけではなかった。
整骨院は、基本的には保険を使った診療を行う。保険とは、けがをしたとか、捻ってしまったとか、明らかな原因があって負傷した場合に適用されるべきものだ。
しかし実際には、慢性的な腰痛や膝の痛みなどに対しても、無理やり適用させているのが整骨院の現実だった。
「40名分のカルテを明日までに持ってきてください」
そんな指導を受けても、カルテをそのまま持っていってはならない。
体のどの部分にどんな治療をし、どんな結果だったを記録する「患者さんを治していくためのカルテ」ではなく「保険請求を満たすためのカルテ」が必要だからだ。
徹夜で40名分のカルテを用意し、持参する。
担当者とのやり取りは、髙木には「もっと上手にごまかしなさいよ」といわれているような気分になることもしばしばだった。
免許をなくすかもしれないという危機感と、連日課せられる指導で身も心もへとへとになりながら、髙木は考えた。
今の保険の制度、そもそも整骨院の在り方は、おかしいのではないか。
良かれと思ってやったことが違反になる。
患者さんにはもっとこうしてあげたいと思ったことを、公にやることができない。
自分がいくら一生懸命やっても、現状の制度がある限り、そしてその制度の中で仕事をしようと思う限りは、報われることはないのではないか。
「患者さんを治す」という基本的な目的ですら、どんどん捻じ曲げられてしまうのではないか。
調査が終わり、結果を待つまでの間は診療をすることはできない。
その間、髙木は考えた。
自分は患者さんを治したいんだ。そのためにはどうすればいいのか。
ぐるぐると思考を巡らせ、行きついた先に出た答え。いや、これ以外にも答えはあるのではないかと何度か考え直した。
しかし結局、いつも到達する答えはそこしかない。
保険を辞めて、すべて自費の診療を行う。
その時、厚労省から通知が届いた。
免許はく奪ではなく「指導」。
治療家として活動を続けることができる。その知らせは、髙木の出した「自費診療を行う」という答えを後押ししてくれるかのように思えた。
髙木:「しんどい時間でしたよ。こんなことを正直に話すのも、治療家としての信頼を損ねるんじゃないかとも思いました。でも、あの件があったから今の私の院があるんです。あの時に摘発されずにいたら、ずっと慰安メインの、保険をごまかしごまかし活用する整骨院でやっていたんじゃないでしょうか。「何か違うなぁ」なんて思いながら(笑)。」
「必ず治す」、自費診療移行への第一歩
 診療を再開すると同時に、自費診療への移行を始めた。保険を使わないで治療をする。これは、治療の制限がなくなる代わりに患者さんへの請求金額も高くなることを意味する。
診療を再開すると同時に、自費診療への移行を始めた。保険を使わないで治療をする。これは、治療の制限がなくなる代わりに患者さんへの請求金額も高くなることを意味する。
これまで窓口で数百円しか支払ってこなかった患者さんに対して「明日からは5,000円です」と伝えるのは、とても難しい。特に保険診療しかやってこなかった髙木にとっては、その一言は「もう来院しなくていいですよ」と言っているに等しいと思えるほどの重みがあった。
そして、それほどの金額を請求するからには、それなりの治療をしなくてはならない。
しかしもともと髙木には、「患者さんの不調を治す」というぶれない目的があり、そのために二つの学校に通い、その後も鍼灸を中心に学びを続けてきた。勉強をしたという点においては、強い自負があった。
そして、鍼灸を学んだ時に言われた、忘れられないあの言葉。
1人でも多くの患者さんの体に触れなさい。
鍼を打つのは誰でもできる。早く感覚を育てなさい。
とにかく、一人でもの患者さんを治そう。実績が持てれば評判が人を呼び、保険を使わない診療でも求めてやってくる人が増えるはずだ。
髙木はそう考え、ひたすら治療に専念した。
髙木の考えは、ほぼ的中した。
ずっと目指していた、重症患者を短期間で改善させる鍼灸の治療法により、たとえ重度のぎっくり腰であっても1~2回の治療で改善させることができるようになった。
そんな実績が増えていくに従い、やがて「あの先生は、鍼ですぐに治してくれる」という評判が生まれた。紹介による来院が増え、重症とされる患者さんの割合が徐々に増していった。
「ずいぶん楽になりましたわ」
「先生、すごいわぁ」
こんな言葉をかけられることも増えた。
ここで自ら成長を止める治療家も、きっと少なくないだろう。ある程度は保険を使った診療で人を集め、本当に重症の患者さんには、自費診療を施す。双方が、高い満足度を得る。
しかし髙木はそうではなかった。
なぜ、満足しきれなかったのは、その理由は二つある。
ひとつは、重症の患者さんの7~8割は治してあげることができたが、同じように治療をして、同じように生活指導をして、同じように通ってもらっても、なかなか治らない患者さんが2~3割いたこと。
「いや、でも8割近く治せているんだからいいじゃないか」
と割り切ることもできるかもしれない。でも、髙木にはそう思えなかった。なぜ治らないのか、なぜ治せないのか、自分がその理由を明らかにできなくてどうする。そんないら立ちもあった。
そしてもう一つの理由として、もっと鍼灸の良さを広め、自費診療を望む患者さんを増やしていきたいと思っていること。
髙木は、鍼灸で体が良くなるという素晴らしい事実を、一人でも多くの人に知ってもらいたかったし、知ってもらうことが自分の役目だとも思っていた。
なのに現実には「鍼は怖いので」と言って遠慮する人もいたし、そもそも保険診療を希望する人数に対して、自費診療を希望する人は絶対的に少なかった。
もっと、自費の割合を増やしていかなければならない。
「もっと、たくさんの患者さんに来てもらわなくては」
本格的な自費診療への移行のための、集患活動が始まった。
髙木:「集患、いわゆる集客をしなきゃならないと、必要性を強く感じましたね。でもその点に関してはほとんどやったことがないので、経営塾に入って学んだんです。
そこでは僕以上に治療に対する意識が高く、集客もうまくいっている治療家がたくさんいました。もちろん皆、自費診療で成功しています。そこでの出会いはものすごい刺激になりましたね。この塾に入れば自費移行もうまくいくし、思い描く治療院をつくれる、と思いました。」
経営塾とは言っても、自身の治療技術と知識を、体のことで困っている患者さんのためにフル活用することを惜しまない、志の高い治療家軍団だ。
髙木は、そこで出会う一人一人から多くのことを学んだ。
安い診療で人を集めて、治療というものの価値を落としてはならない。
本当に良いものを提供する治療家にならなくてはいけない。
自身の、そして院の在り方を、考えを変えていくうちに、髙木はひとつの大きな決断をした。
自費診療の値上げ。
数回の段階を経て当初の倍以上の金額に設定した。
それによって、予想していた通り様々な変化があった。
まず、より重症な患者さんが来る。
健康というものを何より大切に思っている人が来る。
そして、髙木へ高い期待と信頼を寄せている。
それらは髙木が望んでいたことであり、また、髙木をさらなる高みへと導くものだった。
「8割治せばいいなんて、甘い考えはもうダメやな。一人残らず治さんと、ただの詐欺師になってしまう」
いくら優秀な子供でも、毎回のテストで100点を取り続けるのは至難の業だ。それに、そこまでやらなくても90点や95点を取り続ければ、それで十分「勉強のできる子」とされる。
治療家の世界も、似たようなところがあるかもしれない。
いくら「素晴らしい」とされる治療技術でも、すべての人を改善させることはできない。原因はわからないがほかの人のようには治っていかない患者さんが、必ず現れてしまう。そして、それを「仕方ない」と割り切る治療家もいる。
しかし髙木はそうではない。
常に100点を取らなければならないと思っている。
全ての患者さんに「良くなったよ」という言葉を言ってもらわなくてはならないと思っている。
その強い思いはやがて、2~3割の患者さんを治すことができない現状へ強い罪悪感を募らせ、髙木に様々な試みをさせることになる。
治療技術の勉強をし直したり、セミナーに行ったり。また、自身でセミナーを開催することもあった。
どこかに「2~3割の患者さんを治しきれない自分」を超えるヒントはないか。この最後のひと山は、どうやって乗り越えたらいいのか。
治療のすべてを明らかにしてくれる学問との出会い
 どこかに答えはないか。
どこかに答えはないか。
さまよっていたその時、髙木は一人の治療家と出会った。出会いは経営塾。難治性の患者さんを治すだけでなく、説明や生活指導も素晴らしいと評判の先生だ。
あるとき、その先生に自分の治療の悩みを打ち明けてみた。「8割は治せる。でもどうしても残り2割は満足のいく結果に導けない。これは個人差として仕方ないと思わなければならないのか」と。
すると答えはすぐに返ってきた。
「いやいや、治りますよ。体のことをもっと深く理解すれば」
そこから始まった先生の話は、治療に関する勉強は怠ってこなかったはずの髙木でさえ、驚かせるものだった。まず、知識の量が比ではない。そして髙木の悩みを解決するヒントすらもすぐに見つけられた。
「すごい・・ 何を学んだら先生みたいになれるんですか」
先生は、ひとつの学問体系の名前を口にした。髙木には聞き慣れないものだったが、次の瞬間にはその学問を学ぶことを決めていた。
「これで8割どまりでなく、10割の患者さんを治せるようになるはずだ」
その学問に基づく治療例は目を見張るものがあった。一瞬で体をパッと変えてしまう。そのためには生半可な知識と実務では足りない。体のこと、それも現在の体だけでなく過去の状態から未来まで、全てを見通せるようにならなければならない。
髙木の学びの日々が再び始まった。
学べば学ぶほど、なぜ自分が今まですべての患者さんを治しきることができなかったのか、理解することができた。
そしてそれを理解したということは、「もう治せる」ということだ。
その確信は数字に表れた。
リピート来院数が増え、自費診療の希望者が増えた。患者さんの満足度も上がり、「この人は治せなかった」と悩むことがなくなった。
また、髙木の治療方針も確立された。元々、「痛みを取る」「再発しない体を作る」ということを目指してやってきた。それに加えて「20代の頃のように歩けるようになる」、これを目指している。
人にとって、歩くという行為は生活を支える大事なものだ。歩けなくなれば、通常の生活はままならなくなる。介護も必要になる。
裏を返せば、「歩く」ができる限り人は元気に、不自由なく暮らせるのだ。
髙木は患者さんの体を見るとき、いつも「どうやったら歩けるようになり、また歩き続けられる体になるか」を考えている。
全ての人が自分の力で歩けるようになるために
 その学問を学んだことで、患者さんのみならず、世間に蔓延している痛みや不調に対する誤解や、誤解を抱えているがために正しい治療を受けることができなくてただただ悪くなっていくばかりの人たちにも、目が向くようになった。
その学問を学んだことで、患者さんのみならず、世間に蔓延している痛みや不調に対する誤解や、誤解を抱えているがために正しい治療を受けることができなくてただただ悪くなっていくばかりの人たちにも、目が向くようになった。
今は、自分が作った院で、そこに来てくれる患者さんの不調に向き合い、一生懸命治療をしている。
しかし髙木の思いはそこだけにとどまらない。
髙木:「痛いところをむやみに温める人とか、何もしてくれない病院にだらだらと行き続けて悪くなっていくばかりの人とか、たくさんいます。もちろんそんな人たちをも当院に呼び込みたいという思いはありますが、それだけでなく、正しい知識を広めるための活動もしていきたいですね。セミナーなんて言ったら堅苦しくて集まらないかもしれないけど、健康情報交換会みたいな形でもいいんでね。何かやれればと思っています。」
今や多くのスタッフを抱える、規模の大きな治療院の院長となった髙木に、「治療家としての今後の目標は?」と尋ねてみた。
すると、きっぱりとこんな答えが返ってきた。
「どなたも『痛いな』と思ったらまず病院に行くと思うのですが、それを「まずは治療院へ」が常識になるようにしていきたいですね。
治療院が増えているとは言っても、まだまだ全ての人の生活に密着しているとは言えません。治療院がもっと身近に存在し、『何かあったら相談しよう』と思われるように、働きかけていきたいと思っています」
気を引き締め、患者さんと向かい合う日々
 「病院でね、この痛みは年齢性のものだからどうしようもないって言われて」
「病院でね、この痛みは年齢性のものだからどうしようもないって言われて」
「手術するしかないって言われて」
「どこに行っても、結局全然良くならなくて」
新しく来院する患者さんの、こんな前置きに続くのはこの言葉だ。
「でもここなら治してくれるって聞いたので来ました」。
髙木はそんな、辛い状況にありながらも希望を持ち続けて来院してくれる患者さんを、優しく迎え入れる。そう、こんなにも「痛みを取りたい」「健康になりたい」と心から願っているのだから、治療家として本気で応えなければならない。
慣れ、飽き。髙木にはそのような状態はない。毎日が、新たな気持ちで迎えなければならない真剣勝負の日なのだから。
「大丈夫ですよ、必ず治りますから」。
今日も新たな気持ちで、この言葉を発している。